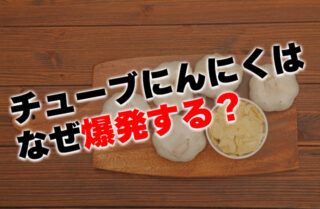GHPチラーとは?仕組み・メリット・EHPとの違いを徹底解説
2025.09.16
近年、企業や公共施設を中心に空調設備のあり方が見直されています。背景には「省エネへの取り組み」「電力料金の高騰」「災害時の事業継続(BCP)」といった社会的な課題があります。特に夏場や冬場のピーク時には電力使用量が急増し、契約電力や基本料金の上昇につながるため、空調設備の選定が経営課題そのものとなるケースも増えてきました。
こうした中で注目を集めているのが「GHPチラー」です。GHPチラーとは、ガスを燃料とするエンジンでコンプレッサを駆動し、冷水や温水をつくり出す空調システムのこと。従来の電気式チラー(EHP)と比べて電力使用量を大幅に抑えることができ、電気料金の削減やピークカットに効果を発揮します。また、機種にもよりますが災害時や停電時にもガス供給が確保されていれば稼働が可能であるため、BCP対策の観点からも高い評価を受けています。
本記事では、GHPチラーの仕組みや特長をはじめ、導入によって得られるメリット、さらにはEHPや吸収式冷温水機との違いまでを分かりやすく解説します。空調の更新や新設を検討している方にとって、最適な選択肢を考える一助となれば幸いです。
GHPチラーとは?

GHPチラーとは、ガスエンジンを動力源として冷暖房用の冷水・温水をつくる空調システムです。一般的に「チラー」とは水を冷却・加熱して循環させる仕組みを指しますが、その駆動方式には大きく分けて「電気式(EHP)」と「ガス式(GHP)」があります。
通常、オフィスビルや工場、学校、病院などの大型建物では、多数の室内機を稼働させるために大規模な冷温水システムが必要となります。従来は電気モーターでコンプレッサを動かすEHPチラーが主流でしたが、電力使用量の増大や電気料金の高騰により、ガスを燃料とするGHPチラーが再び注目を浴びています。
GHPチラーの仕組み
GHPチラーでは、都市ガスやLPガスを燃料とするエンジンでコンプレッサを回転させ、冷媒を圧縮。その冷媒を熱交換器に通すことで、冷水や温水を生成します。生成された冷温水は配管を通じて建物全体に供給され、各室内の空調に利用されます。電気をほとんど使わずガスで稼働する点が最大の特長です。
EHPとの違い
EHP(Electric Heat Pump)との大きな違いは「動力源」です。EHPは電気モーターでコンプレッサを動かすのに対し、GHPはガスエンジンで動かします。この違いによって、以下のような特徴が生まれます。
| 電力ピークカット効果 | EHPは稼働時に多くの電力を消費しますが、GHPは電気使用量が少ないため契約電力を抑えやすい。 |
|---|---|
| ランニングコストの安定 | 電気料金の変動リスクを回避できる。ガス料金も影響はあるが、電気料金と分散できるため全体のバランスが取りやすい。 |
| 環境対応 | 近年の高効率型GHPはCO2排出量の低減にも寄与。さらにエンジンの排熱を有効活用すれば、給湯や融雪などにも利用可能。 |
チラーとパッケージエアコンの違い
一般的なパッケージエアコンは室外機と室内機を直接つないで冷媒を循環させますが、チラー方式は「水」を介する点が異なります。そのため、冷媒配管を長距離にわたって敷設する必要がなく、建物規模が大きい施設や複数の建物をまとめて空調する場合に有効です。GHPチラーはこの仕組みにガスエンジンを組み合わせることで、大規模かつ省エネな空調を実現します。
GHPチラーの仕組みと特長

仕組みの概要
GHPチラーの基本構造は、従来のチラーと同様に「冷媒を圧縮 → 熱交換器で熱を移動 → 冷水・温水を生成 → 建物へ供給」という流れです。大きな違いは、その駆動源が電気モーターではなくガスエンジンである点です。
都市ガスやLPガスを燃料とするエンジンがコンプレッサを回転させ、冷媒を圧縮します。圧縮された冷媒は熱交換器を通じて冷水や温水を作り出し、それを建物内の空調機器やファンコイルユニットに供給。こうして冷暖房が行われます。つまり、エネルギー源を「ガス」に切り替えることで、電力使用量を大幅に抑えられるのが最大のポイントです。
特長1:電力ピークカット
最大の特長は、電力ピークカット効果です。EHPチラーは大量の電力を消費するため、契約電力が高くなりやすいのに対し、GHPチラーはガスを主燃料とするため電力消費を大幅に削減可能。結果として、契約電力の抑制や電気料金の削減につながります。特に夏や冬のピーク時に電力使用量を分散できるのは、電力料金高騰が続く昨今の大きなメリットです。
特長2:高い省エネ性
ガスエンジンは部分負荷運転(空調負荷が少ない時の運転)でも効率が落ちにくく、省エネ性に優れています。さらに、エンジンの排熱を利用することで給湯や床暖房にも活用でき、エネルギーを無駄なく使う「コージェネレーション的」な使い方が可能です。
特長3:安定した冷暖房能力
EHPは外気温の影響を受けやすく、低外気温下では暖房能力が低下する課題があります。一方、GHPチラーはエンジン駆動のため低外気温環境下でも安定して稼働し、寒冷地や冬場でも確実に熱を供給できる強みがあります。
特長4:災害・停電時にも有効(一部の機種)
ガス供給が確保されている限り、停電時でも稼働できる点も大きな魅力です。災害対策(BCP)の一環として、病院や福祉施設、避難所などに導入する価値が高い設備といえます。
特長5:静音・快適性
最新のGHPチラーは騒音や振動を抑えた設計になっており、都市部や住宅に隣接する施設でも安心して導入可能です。冷暖房の立ち上がりも早いため、快適性の面でも優れています。
GHPチラーのメリット
GHPチラーの導入によって得られる利点は多岐にわたります。ここでは代表的な4つの観点から解説します。
メリット1:電気料金の削減とコスト安定化
GHPチラーの最大のメリットは、電力消費量を大幅に削減できることです。EHPチラーはコンプレッサを電気モーターで駆動するため、大規模施設ではピーク時の電力需要が非常に高くなります。その結果、契約電力が増え、基本料金が跳ね上がるケースが多く見られます。
一方、GHPチラーはガスを主燃料として動くため、電気の使用量は最小限に抑えられます。これにより、契約電力を低く維持でき、電気料金の基本料金削減につながるのです。また、電気とガスでエネルギー源を分散できるため、電気料金の値上がりリスクを軽減し、ランニングコストを安定化できる点も重要なメリットです。
メリット2:省エネ・環境性能の向上
GHPチラーはエンジン排熱を有効活用できるため、給湯や床暖房、温水プールの加温など多用途に利用可能です。これにより、一次エネルギーの利用効率を高め、トータルでの省エネ効果を実現します。
さらに、近年の高効率型モデルではCO₂排出量を従来比で削減可能。省エネ法や環境基準への対応を求められる自治体や企業にとって、CSRやESGの観点からも導入価値が高まっています。
メリット3:快適性の向上
GHPチラーは立ち上がりが早く、冷暖房を開始してから短時間で快適な室温に到達できます。EHPは外気温に影響を受けやすく、特に寒冷地や真冬の朝方には暖房能力が低下する傾向がありますが、GHPは低外気温下でも安定した能力を発揮します。
また、部分負荷運転でも効率を維持できるため、冷暖房の過不足が少なく、建物全体を安定した温度に保ちやすい点も評価されています。利用者にとっては「どの部屋にいても快適」という安心感につながります。
メリット4:BCP(事業継続計画)対策に有効
自然災害や停電時においても、ガス供給さえ確保されていればGHPチラーは稼働できます。特に病院や介護施設、公共施設では「空調停止=生命や安全へのリスク」に直結するため、停電に強い空調システムは大きな導入メリットとなります。
災害時に冷暖房を維持できれば、避難所機能を果たす施設としての信頼性も高まります(一部の機種のみ災害時も稼働)。電気に依存しすぎない仕組みを備えることは、企業や自治体にとって重要なリスク分散策といえるでしょう。
メリット5:長期的な運用での安心
GHPチラーは耐久性が高く、適切なメンテナンスを行えば長期間にわたって安定稼働が可能です。さらに、ガス供給インフラが整っている都市部では、導入後の運用コストを見込みやすく、将来のコスト計画が立てやすいのもメリットの一つです。
このように、GHPチラーは「コスト削減」「環境対応」「快適性」「災害時の安心」といった多方面で効果を発揮します。単に電気料金を抑えるだけではなく、エネルギーの多様化やリスクマネジメントの観点からも価値の高い空調システムといえるでしょう。
他方式との比較
GHPチラーを検討する際に欠かせないのが、従来の空調方式との比較です。ここでは、主に EHPチラー(電気式) と 吸収式冷温水機 の2つと比べて、それぞれの特性と使い分けのポイントを整理します。
EHPチラーとの比較
EHP(Electric Heat Pump)チラーは、電気モーターでコンプレッサを駆動し、冷媒を循環させて冷水や温水をつくる仕組みです。一般的に、ビルや工場で広く採用されています。
| 動力源 | EHP=電気、GHP=ガスエンジン |
|---|---|
| 電力使用量 | EHPは多い、GHPは少ない |
| 契約電力 | EHPは高くなりやすい、GHPは抑制可能 |
| 外気温の影響 | EHPは低外気温下で効率低下、GHPは安定稼働 |
| メンテナンス | EHPはシンプル、GHPはガスエンジンの定期点検が必要 |
EHPは電気一本でシンプルに運用できる点が魅力ですが、電気料金の高騰やピーク電力問題が課題です。一方でGHPは電気依存を軽減でき、ピークカット効果が期待できるため、大規模施設や電力契約を抑えたい建物で有効です。
吸収式冷温水機との比較
吸収式冷温水機は、ガスや蒸気ボイラーを熱源とし、水を冷却または加熱する方式です。冷媒として水や臭化リチウムを用いる点が特徴で、かつては大規模施設で多く採用されていました。
| 動力源 | 吸収式=熱源(ガス・蒸気)、GHP=ガスエンジン |
|---|---|
| 設備規模 | 吸収式=超大規模向け、GHP=中〜大規模向け |
| エネルギー効率 | 吸収式は部分負荷時に効率が低下しやすい、GHPは安定 |
| 設置スペース | 吸収式は大型でスペースを取る、GHPは比較的コンパクト |
吸収式は、工場の廃熱や蒸気を有効活用できる環境ではメリットが大きい方式です。しかし、エネルギー効率や維持管理の点ではGHPチラーに軍配が上がるケースも増えています。
方式ごとの向き不向き
| EHPチラー | 電力コストが安定しており、メンテナンスを簡略化したい施設向き |
|---|---|
| 吸収式冷温水機 | 工場や病院など、ボイラー熱源や廃熱を有効活用できる大規模施設向き |
| GHPチラー | 電気料金の削減、ピーク電力対策、災害時の稼働性(一部の機種のみ)を重視する中〜大規模施設向き |
このように、GHPチラーは「EHPの電気依存」と「吸収式の大規模特化」の中間に位置する技術です。電力コストを抑えつつ、ガスによる安定稼働と環境性能を両立できる点が、他方式にはない大きな魅力といえるでしょう。
活用シーン

GHPチラーは「省エネ性」「ピークカット効果」「災害時の稼働性(一部の機種のみ)」といった特徴から、さまざまな施設で導入が進んでいます。ここでは、代表的な活用シーンを一般的な用途別に整理して紹介します。
医療・福祉施設
病院や介護施設は、冷暖房だけでなく、給湯や湿度管理といった機能も求められる環境です。特に入院患者や高齢者が快適かつ安全に過ごすためには、24時間安定した空調運転が欠かせません。
GHPチラーはガスを燃料とするため、停電時にも稼働できる安心感があります(一部の機種のみ)。災害時に空調が止まってしまうと医療機能に重大な影響が出るため、BCP対策を重視する医療・福祉施設に適した空調システムといえるでしょう。
学校・教育施設
学校は教室や体育館など、多様な空間を持つ大規模施設です。授業や行事などで長時間空調を稼働させるため、電力料金の負担が課題となりやすい環境でもあります。
GHPチラーを導入すれば、電力使用量を大幅に抑制でき、契約電力の削減にもつながります。さらに、部分負荷運転に強い特性から、季節や時間帯に応じて効率よく冷暖房ができ、学習環境の快適性を維持しながら省エネ運営が可能になります。
工場・倉庫
工場や物流倉庫は、大空間の温度管理が課題となるケースが多い施設です。EHPの場合、大規模な電力を必要とするため契約電力が膨らみやすく、コスト負担が大きくなります。
その点、GHPチラーはガスエンジン駆動のため電力使用量を抑えられ、広い空間を効率的に空調できるのが強みです。また、低外気温でも暖房能力が落ちにくいため、冬季の作業環境改善にも有効です。
オフィスビル・商業施設
オフィスや商業施設では、テナント数や利用者数の増減によって空調負荷が変動します。そのため、柔軟な制御と省エネ性能が求められます。
GHPチラーは部分負荷時の効率が高く、必要な分だけの出力で運転可能。結果として、余分なエネルギー消費を抑え、テナントオーナーや管理会社にとって運用コスト削減につながるのが魅力です。さらに、環境配慮型の空調を導入することで、企業のESG評価や入居者へのPR効果も期待できます。
公共施設・避難所
市役所や体育館といった公共施設は、災害時には避難所としての役割を果たします(一部の機種のみ)。その際に空調や給湯を維持できるかどうかは、避難者の生活の質や安全性を大きく左右します。
GHPチラーはガスインフラが確保されていれば一部の機種のみ停電時も稼働できるため、災害に強いインフラ設備として注目されています。公共施設におけるBCP対策の一環として導入が進む理由はここにあります。
このように、GHPチラーは「病院や学校などの公共性が高い施設」から「工場やオフィスなどの大規模業務施設」まで、幅広い分野で活躍しています。単なる空調設備にとどまらず、コスト削減・快適性・安全性を同時に満たす総合的なソリューションとして導入価値が高いのです。
導入のポイントと注意点
GHPチラーは、省エネ性や一部の機種に限り災害時の安心感など多くのメリットを持ちますが、導入を検討する際にはいくつかのポイントと注意点を押さえておく必要があります。適切に計画・設計を行うことで、その効果を最大限に発揮できます。
初期投資とランニングコストのバランス
GHPチラーはEHPに比べると本体価格が高めになる傾向があります。そのため、導入時の初期投資は大きくなる可能性があります。ただし、契約電力の削減やランニングコストの安定化効果を考慮すると、中長期的には十分に投資回収が可能です。導入を検討する際には、ライフサイクルコスト(LCC)の視点でシミュレーションを行うことが重要です。
ガス供給設備の確認
GHPチラーはガスを主燃料とするため、ガス供給体制の有無や供給量が導入の前提条件となります。都市ガスが供給されているエリアであればスムーズに設置可能ですが、LPガスの場合は貯槽の設置やガス供給契約の調整が必要になることもあります。導入検討時には、建物の立地条件やガスインフラ状況を事前に確認しておくことが不可欠です。
メンテナンス体制
EHPに比べて、GHPはガスエンジンの定期点検や部品交換が必要です。自動車のエンジンと同様、稼働時間に応じてオイル交換やフィルター交換などのメンテナンスが求められます。これを怠ると効率低下や故障リスクが高まりますので、定期的な点検・保守契約を前提に導入することが推奨されます。
建物規模・用途に応じた最適設計
GHPチラーは万能な空調方式というわけではなく、建物規模や用途に合わせた設計が欠かせません。
| 大規模工場や倉庫 | ピークカット効果を重視 |
|---|---|
| 学校・オフィス | 部分負荷時の効率を重視 |
| 医療・福祉施設 | 停電時の稼働性や信頼性を重視(一部の機種のみ災害時稼働) |
といったように、施設ごとのニーズを考慮して設計することが大切です。
将来のエネルギー環境を見据える
エネルギー価格は不安定であり、将来的な電気料金やガス料金の変動を見込んだ上での判断が求められます。再生可能エネルギーの活用や分散型エネルギーシステムとの組み合わせなど、中長期的なエネルギー戦略の中で位置づけることが成功のポイントです。
このように、GHPチラーを導入する際には「初期費用」「ガスインフラ」「メンテナンス」「用途適合性」「将来性」といった視点で検討することが欠かせません。事前にシミュレーションや専門業者への相談を行い、自社施設に最適なシステム設計を行うことが、長期的な安定運用のカギとなります。
まとめ
GHPチラーは、ガスエンジンを動力源とすることで電力消費を大幅に抑えられる次世代の空調システムです。電気式(EHP)と比べて契約電力を下げやすく、電気料金の削減やランニングコストの安定化に大きな効果を発揮します。さらに、低外気温でも安定した暖房性能を維持できるほか、エンジン排熱を有効活用できる点も省エネや環境対応の観点から高く評価されています。
また、ガスインフラが確保されていれば停電時にも稼働できるため、BCP対策の一環として病院や福祉施設、公共施設などでも注目を集めています。学校や工場、オフィスビルといった大規模施設においても、快適な空調環境を維持しながらコスト削減を実現できる点は大きな導入メリットです。
一方で、初期投資や定期的なメンテナンスといった注意点もあるため、導入を検討する際はライフサイクルコストやガス供給環境を含めた総合的な判断が欠かせません。
省エネ・環境性能・災害対策(一部の機種のみ)を同時に満たせるGHPチラーは、これからの時代に求められる空調の有力な選択肢といえるでしょう。最適な方式を選ぶためには、EHPや吸収式冷温水機との比較検討を行い、建物の用途や運用条件に合わせたシステム設計を行うことが大切です。