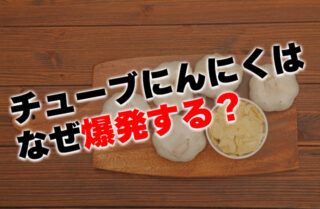「とりあえずやってみる」は危険?アジャイル開発と場当たり対応の違いを解説
2025.10.08
DX推進の現場では「アジャイルで進めよう!」という掛け声のもとに取り組みを始める企業が増えています。
しかし、実際にフタを開けてみると「アジャイル」を名乗りながらも、その実態は「行き当たりばったりの場当たり対応」になっているケースが少なくありません。
経営者からは
「結局ムダが増えてるだけでは?」という不満が、現場担当者からは「とにかくやらされて混乱している」という悲鳴が聞こえてきます。
なぜこんなすれ違いが起こるのでしょうか。
それは「アジャイル=柔軟」「行き当たりばったり=場当たり的」といった言葉のイメージが混同され、正しい理解がされていないからです。
本記事では「アジャイル」と「行き当たりばったり」の違いを整理し、中小企業のDX推進の実務にどう活かせるかを具体的に解説していきます。
アジャイル開発の本質
アジャイルという言葉はもともとソフトウェア開発の世界から生まれた考え方です。2001年に「アジャイルソフトウェア開発宣言」が提唱され、従来の「ウォーターフォール型開発(最初に計画を立てて一気に作り込む方式)」の限界を補う手法として広まりました。
「小さく早く試す」ことに価値がある
アジャイルの最大の特徴は、「小さく始め、短いサイクルで改善を繰り返す」ことです。
- 大規模な計画を立てて何年もかけて仕上げるのではなく、数週間単位で試作(プロトタイプ)をつくる。
- その都度、利用者の声を聞きながら改善を加える。
- 失敗してもダメージが小さいので、すぐに方向修正できる。
このアプローチにより、変化の速い市場や顧客ニーズに柔軟に対応できるのです。
ゴールは「顧客に価値を届けること」
「アジャイル=場当たり的に進める」と誤解されがちですが、実際はまったく逆です。
アジャイルは最初に「顧客にどんな価値を提供したいか」というゴールを明確に定めます。そのうえで、道筋を小さく分割して検証しながら進める手法です。
たとえば、DX推進におけるkintone導入を考えてみましょう。
- いきなり全社一斉に大規模アプリを作るのではなく、まずは一部署で小さく導入。
- 実際に使った社員の声をフィードバックして改善。
- それを繰り返しながら全社展開につなげていく。
これがまさにアジャイル的アプローチです。
チームでの協働と透明性
アジャイルでは「チーム全員で進捗や課題を共有する」ことが重要です。
- 毎日の短いミーティング(デイリースクラム)で状況を確認する。
- 成果物や課題を見える化して、属人化を防ぐ。
- 「誰がどこまで進めたのか」「次に何をするのか」をチーム全体で把握する。
こうした透明性があるからこそ、改善のサイクルを正しく回せるのです。
行き当たりばったりの典型例
アジャイルと混同されやすいのが「行き当たりばったりの進め方」です。表面的には「まずやってみる」「早く動く」といった点で似ているため、違いがわかりにくいのですが、その本質は大きく異なります。
ゴールが曖昧なままスタート
行き当たりばったりの最大の特徴は、そもそも「何を達成したいのか」が明確になっていないことです。
例えば「DXを進めたいから、何か新しいツールを入れてみよう」と導入を決めても、導入目的や解決したい課題がはっきりしていなければ、ただの“お試し導入”に終わります。
結果として、導入したツールは社内で活用されず、経営層から「結局ムダな投資だった」と見られてしまうのです。
記録や検証がない
アジャイルは「改善サイクル」が前提ですが、行き当たりばったりでは「とりあえずやって終わり」になりがちです。
検証をせずに次の施策へ移るため、同じ失敗を繰り返すことになります。
よくあるのが、RPAの導入で一部の社員だけがロボットを作り、トラブルが起きても記録を残さず放置。結局「ロボットが止まったまま数日間誰も気づかなかった」という状況です。これでは効率化どころか、かえってリスクを増大させてしまいます。
判断基準が人によってバラバラ
行き当たりばったりな進め方では、意思決定の軸が共有されていません。
「この機能は必要だ」「いや、優先度が低い」など、人によって判断が異なり、会議のたびに方向性が変わる。
現場社員からすると「昨日と言っていることが違う」「結局どっちをやればいいのか分からない」と混乱を招きます。結果、モチベーション低下や“やらされ感”が生まれてしまいます。
成果が積み上がらない
アジャイルは小さな成功や学びを積み重ねて大きな成果に育てていきますが、行き当たりばったりは「その場しのぎ」で終わるため、知見やノウハウが組織に残りません。
「新しいツールを入れたけど定着せず廃止」「別の部署でまた別のツールを入れる」――これを繰り返すと、社内のシステムがバラバラに乱立し、むしろ業務が複雑化してしまうのです。
まとめ
行き当たりばったりな進め方は、一見スピード感があるように見えて、実際には「迷走」を招きます。
- ゴールが曖昧
- 検証がない
- 判断基準が共有されない
- 成果が残らない
これらが積み重なると、現場からは不満が噴出し、経営層は「DXはもうやめよう」と判断してしまうリスクすらあります。
両者の決定的な違い
「アジャイル」と「行き当たりばったり」は、表面的には似た部分があります。どちらも「完璧な計画を立てずに進める」「変化に応じて修正する」というスタイルを取るからです。
しかし、その本質には大きな違いがあります。
ゴールの有無
| アジャイル | 最終的に「顧客や利用者にどんな価値を届けたいか」というゴールを明確に定める。そのうえで小さく区切って進める。 |
|---|---|
| 行き当たりばったり | ゴールが曖昧、あるいは存在しない。だから進めるごとに方向性がブレ、無駄が増える。 |
例:kintone導入で「全社の情報共有を効率化する」というゴールを持ってアプリを一つずつ検証して展開していくのはアジャイル。一方で「とりあえず作ってみよう」でアプリが乱立し、誰も使わないのは行き当たりばったり。
プロセスの有無
| アジャイル | 短いサイクルで「計画 → 実行 → 振り返り → 改善」を繰り返すプロセスが存在する。 |
|---|---|
| 行き当たりばったり | プロセスがなく、「やって終わり」「思いつきで方向転換」。改善や学びが次につながらない。 |
RPA活用で「ロボを作成 → 動作検証 → 振り返り →共有」を仕組みにしている会社はアジャイル的。逆に「ロボを作っても記録せず、壊れたら放置」は場当たり的。
判断基準と共有の有無
| アジャイル | 優先順位や判断基準をチームで共有。意思決定の透明性がある。 |
|---|---|
| 行き当たりばったり | 判断が人によってバラバラで、会議のたびに方向性が変わる。 |
これが現場の混乱や「やらされ感」を生む最大の要因。
成果の積み重ねの有無
| アジャイル | 小さな成果や学びを組織に蓄積し、次の改善に活かす。ノウハウが会社の資産になる。 |
|---|---|
| 行き当たりばったり | その場の取り組みが次に残らない。毎回ゼロからやり直す。 |
例えば、ミヨシテックではロボパット導入後「ロボパットマスター認定制度」を作り、属人化を防ぎながら知見を共有している。これはアジャイル的仕組み化の好例。
比較を文章で整理
アジャイルと行き当たりばったりの違いを、いくつかの観点から整理してみましょう。
ゴール
アジャイルは「最終的に顧客へどんな価値を届けたいのか」というゴールが明確。
行き当たりばったりはゴールが曖昧、あるいは存在しない。だから進めるたびに方向がブレる。
プロセス
アジャイルには「計画 → 実行 → 振り返り → 改善」という小さなサイクルがある。
行き当たりばったりはプロセスがなく、「とりあえずやって終わり」。改善が積み重ならない。
判断基準
アジャイルでは優先順位や判断基準をチームで共有する。意思決定が透明でぶれにくい。
行き当たりばったりでは、人によって判断がバラバラ。会議のたびに方向性が変わり、現場が混乱する。
成果の積み重ね
アジャイルは小さな成果や学びを残し、組織に蓄積される。ノウハウが資産になる。
行き当たりばったりは成果がその場限りで、次に活かされない。毎回ゼロからやり直す羽目になる。
まとめ
アジャイルは「柔軟に変化に対応する仕組み」であり、行き当たりばったりは「仕組みなき迷走」です。
見た目は似ていても、ゴール・プロセス・共有・成果の有無で雲泥の差があります。
DX推進において「アジャイルのつもりが実は行き当たりばったり」になっている企業は少なくありません。この違いを理解することが、DXを成功に導く第一歩です。
ありがちな誤解と失敗例
「アジャイルでやっているつもり」が、実はただの行き当たりばったりに陥っているケースは少なくありません。ここでは中小企業のDX推進現場でよく起こる誤解と失敗例を紹介します。
「とりあえずやってみよう」がアジャイルだと思っている
アジャイルは「小さく試す」ことが特徴ですが、それは“仮説と検証のサイクル”が前提です。
ところが現場では「とりあえずやろう」「まずやってみよう」だけが独り歩きし、結果的に記録も検証もないまま施策が乱立。
- ツールを導入しても誰も使わず放置される
- 「また新しいシステムが来た」と社員の不満が募る
- 経営層から「DXは金食い虫だ」というレッテルを貼られる
これはアジャイルではなく、単なる思いつきによる試行錯誤にすぎません。
kintoneアプリの乱立問題
kintone導入企業でよく見られるのが、「社員が自由にアプリを作っていい」とした結果、目的が曖昧なアプリが大量に乱立してしまうケースです。
- 類似アプリが何個も存在する
- どのアプリに入力すればいいのか社員が迷う
- 結果的に紙やExcelに戻ってしまう
これは「小さく試したつもり」が、実は設計思想のない場当たり対応だったという典型例です。アジャイルなら必ず「目的を定め、検証し、不要なものは整理する」というステップを踏むはずです。
RPA導入の“ロボ放置”
RPAツール導入時にも似た失敗が起こります。最初は「社員が自分でロボを作れる」ことを強調し、自由に開発を進めます。
しかし運用ルールや振り返りの仕組みがないと、こんな事態が発生します。
- 作った本人しかロボの中身を理解していない(属人化)
- トラブルが起きても記録や共有がないので誰も直せない
- 結局「ロボが止まっていた」「数日間動いていなかった」と後から判明
これでは効率化どころかリスク増大です。アジャイルなら「改善と共有」が必須のはずですが、それが抜け落ちている状態です。
社内チャット導入の失敗
DX推進でありがちなのが、チャットツールの試験導入です。
「とりあえず一部部署でSlackを使ってみよう」と始めるものの、運用ルールがなく通知も不十分。結果、誰も使わず自然消滅してしまう。
社員からは「結局メールの方が早い」と言われ、せっかくの投資が無駄になる。これもまた“アジャイルごっこ”に終わってしまった典型例です。
共通する原因
これらの失敗に共通するのは、
- ゴールを決めていない
- 検証や振り返りをしない
- 成果や失敗を共有しない
という3点です。
つまり「アジャイルでやろう」と言いながら、その本質である“サイクルを回す仕組み”を持っていないのです。
真のアジャイル的進め方(DXでの実践ポイント)
アジャイルと行き当たりばったりを分ける最大のポイントは「仕組みがあるかどうか」です。
単なる思いつきや試行錯誤で終わらせず、改善を積み重ねて成果を組織の資産にしていく。このために、DX推進の現場で取り入れるべき具体的な実践ポイントを整理します。
ビジョン(ゴール)を明確にする
- DXを進める目的を「システム導入」ではなく「業務や顧客にどんな価値をもたらすか」に設定する。
- 例えば「受発注業務を効率化して残業時間を30%削減する」「問い合わせ対応の待ち時間を半減する」など、具体的な成果イメージを共有する。
ゴールが曖昧なままではアジャイルは機能しません。最初に“なぜやるのか”をチームで合意しておくことが大前提です。
小さく始め、必ず振り返る
- 一度に全社導入を狙うのではなく、小さな部署や業務でパイロット導入する。
- その結果をチームで振り返り、うまくいった点・改善すべき点を明確化する。
- 成果と課題を見える化し、次のサイクルに反映する。
「試して終わり」ではなく、「試して振り返る」を習慣化することがアジャイルの生命線です。
成果物を共有して見える化
- 作成したkintoneアプリやRPAのロボットを社内で共有し、誰でも使える状態にする。
- 改善点や運用ルールをドキュメント化して残す。
- 定例会議や社内チャットで「今回の成果」「次の改善点」をオープンに話す。
成果が共有されることで「やってよかった」が実感でき、経営層も現場も前向きになりやすい。
属人化を防ぐ仕組みをつくる
- RPA導入後に「ロボパットマスター認定制度」を設け、複数人が作成・運用できる体制を整える。
- kintoneアプリ設計のルールを明文化し、誰が見ても理解できるようにする。
- 月1回の勉強会や共有会を開き、情報交換を継続する。
属人化は“行き当たりばったり”の温床。仕組み化によって初めてアジャイルが組織に根づきます。
改善を「次につなげる」習慣
- 振り返りをして終わるのではなく、必ず次のサイクルの改善に反映させる。
- 例えば「今回のアプリで入力漏れが多かった」→「次は必須項目を設定する」といった具体的アクションを決める。
- この“改善の積み重ね”がアジャイルの真価です。
ツール活用の一例
| kintone | 業務フローを小さくアプリ化し、現場の声を反映しながら改善。 |
|---|---|
| ロボパット | 単純業務を自動化し、作成したロボを共有・改善。 |
| 社内チャット(Chatworkなど) | 改善内容やトラブルをリアルタイムに共有。 |
ツール自体がアジャイルを生むのではなく、あくまで「アジャイル的進め方を支えるための道具」として使うことが重要です。
まとめ
アジャイル的に進めるためには、
- 明確なゴール
- 小さな実行と振り返り
- 成果の見える化
- 属人化を防ぐ仕組み
- 改善を次につなげる習慣
この5つが欠かせません。
これらを徹底すれば、単なる“行き当たりばったり”から脱却し、DX推進を持続的に前に進められます。
アジャイルは“柔軟”、行き当たりばったりは“迷走”
ここまで見てきたように、アジャイルと行き当たりばったりは見た目が似ていても本質はまったく異なります。
| アジャイル | 「ゴールを明確にし、小さく試し、振り返って改善し続ける仕組み」 |
|---|---|
| 行き当たりばったり | 「ゴールもプロセスもなく、その場しのぎで迷走する状態」 |
DX推進において「アジャイルのつもり」が実は行き当たりばったりだった、という企業は少なくありません。その結果、経営層からは「ムダが増えただけ」と見られ、現場からは「やらされ感」や「混乱」ばかりが広がってしまいます。
一方で、正しくアジャイルを取り入れた企業は、変化の激しい時代に対応できる柔軟性を手に入れています。小さな成功と学びを積み重ねることで、失敗を恐れず挑戦し続けられる文化が育ち、DXが持続的に進むのです。
読者へのメッセージ
もし今、御社で進めているDXが「思いつきで進んでいる」「現場の不満が多い」「成果が積み上がっていない」と感じるなら、それは“アジャイル”ではなく“行き当たりばったり”に陥っているサインかもしれません。
DX推進を本当に成功させるには、正しくアジャイルを理解し、仕組みとして根づかせることが不可欠です。
最後に
ミヨシテックでは、
-
kintone導入の伴走支援
-
RPAロボパットの定着サポート
-
社内チャット活用やAIプロンプト支援(プロンプトゲート)
など、アジャイル的にDXを進める仕組みづくりをサポートしています。
「アジャイルで進めたいけど、実際は行き当たりばったりになっている気がする」
そんなお悩みがあれば、ぜひ一度ご相談ください。私たちが実際に経験した失敗と成功のノウハウをもとに、御社のDXを伴走支援いたします。