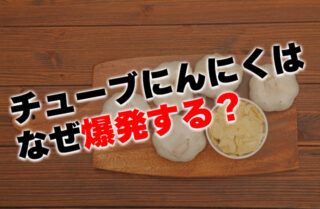残業削減×効率化を両立するRPA運用|ロボパット導入事例と効果
2025.08.09
社員が休んでいる間も進む仕事
朝の出社時、すでに終わっている仕事があるという衝撃
ミヨシテックの社員が朝オフィスに来てパソコンを立ち上げると、
そこには前日まで未処理だったはずの作業が、すべて完了済みの状態で並んでいます。
- 勤怠情報はすでにkintoneの勤怠管理アプリに移行されている
- 各担当者のチャットには「今日提出すべき図面」「期限が迫ったガスや水道の承諾書」が一覧表示
- 前日のアルコールチェック状況も確認済みで、未実施者には通知済み
- 新規案件の情報は職人が使うANDPADにも登録済み
- 大手ハウスメーカーの入退場エラーは通知が送られ、対応待ち状態
- 未承認の受注案件は、担当者に承認依頼が届いている
社員はその通知を確認しながら、すぐに“やるべき仕事”に着手できます。
これは偶然でも、誰かの早朝出勤の成果でもありません。
実は、社員が眠っている間にRPA「ロボパット」が静かに働いていた成果なのです。
「作業を代わりにやる」だけじゃない、ロボパットの真価
RPA(Robotic Process Automation)ツールであるロボパットは、パソコン上の操作を人間の代わりに自動で行ってくれる“デジタルワーカー”です。
Excel入力やデータ移行、システム間連携、通知送信など、ルールが決まっている業務であればほぼ何でも対応できます。
しかし、ミヨシテックの活用は単純な置き換えにとどまりません。
ポイントは、「いつ動かすか」まで設計していることです。
| 夜間に動かすべき業務 | 100名を超える社員の勤怠データのように、誰も操作しない時間帯に進めたい作業 |
|---|---|
| 朝方に動かすべき業務 | 担当者が出社してすぐ確認してほしい通知系作業 |
この時間設計により、ロボはただの作業代行ではなく、業務の流れ全体を最適化する存在になっています。
1つのロボ作成にかかる「3〜4時間」は投資である
ここで多くの人が驚くのが、ロボパットで1つの業務を自動化するロボを作るのに3〜4時間かかるという事実です。
「そんなにかかるなら、作るより自分でやった方が早いのでは?」と考える人もいるでしょう。
しかし、この3〜4時間は単なるコストではなく“未来の時間を買う投資”です。
- 勤怠移行のように毎日3時間かかっていた作業がゼロに
- 期限確認や通知のように毎朝30分〜1時間かかっていた作業が自動化
- 人がやる場合に発生する確認漏れ・転記ミスも防止できる
投資と回収の関係で考えると、
仮に作成に4時間かかっても、毎日30分削減できれば1週間足らずで元が取れる計算です。
しかも一度作ったロボは、条件が変わらない限り毎日正確に動き続けます。
ミヨシテックのロボ活用哲学:「社員が働かない時間」に仕事を進める
ミヨシテックでは、20:00全館消灯ルールを運用しており、残業を減らす取り組みとして実施しています。
しかし、残業を減らすだけでは、業務量が減らなければ結局どこかにしわ寄せが来ます。
そこで発想を転換し、「社員が働かない時間にロボが働けばいい」という考え方を採用しました。
- 夜間は勤怠移行のように時間がかかる処理を黙々と進める
- 朝方は、その日の業務開始に間に合わせたい通知をまとめて送る
こうすることで、社員がパソコンを開く瞬間には“仕事が始まっている状態”を作れるようになりました。
時間帯設計のメリット
RPAの効果は作業削減だけではありません。動く時間を設計することで、次のようなメリットが得られます。
| 社員の集中力を高める | 朝イチで今日のタスクが明確になっているため、すぐ業務に入れる |
|---|---|
| 就業規則を守れる | 夜中に通知を送らないように設定し、勤務時間外の業務指示を回避 |
| トラブル対応のスピード向上 | 朝方にエラーや期限切れ情報を通知することで、業務時間内に処理開始 |
| 残業削減に直結 | 夜間の自動化で翌日に残る単純作業をゼロ化 |
作成時間は“時間口座”への預け入れ
この仕組みをわかりやすく説明するために、ミヨシテックでは「時間口座」という考え方を社内で共有しています。
- ロボ作成=時間口座への預け入れ
- ロボ稼働による時短=毎日の利息
- 利息は日数が経つほど積み上がり、やがて莫大な“時間資産”になる
<例>
- 勤怠移行ロボ(作成4時間)→ 毎日3時間削減 → 2日で元本回収
- 期限通知ロボ(作成3時間)→ 毎日30分削減 → 6日で元本回収
この計算で見れば、「作るよりやった方が早い」という感覚は一瞬で覆ります。
ロボは人の“延長”ではなく“並列稼働”する仲間
もう一つ重要なのは、ロボは社員の延長線上で働く存在ではなく、別のラインで並列稼働する仲間だということです。
人間が休んでいる間、別ラインでロボが仕事を進めておくことで、翌日の業務開始地点がそもそも前倒しになります。
つまり、RPAは「社員の代わりに残業する存在」ではなく、
「社員の横で24時間体制を支える存在」です。
この第1章では、ミヨシテックがなぜ「作成時間=投資」と捉え、夜間・朝方にロボを動かすことで残業ゼロに近づけたのか、その考え方をお伝えしました。
次章からは、この時間帯別ロボの具体的な役割と作業内容を詳しく紹介していきます。
背景:時間帯を意識したRPA運用の必要性
“いつ動くか”を決めることが成果を左右する
RPA導入の効果は、「何を自動化するか」だけで決まるわけではありません。
同じロボでも、動かすタイミング次第で効果は大きく変わります。
ミヨシテックがRPAロボパットを導入した当初、最初に直面した課題は「作業時間帯の最適化」でした。
なぜなら、次のような状況があったからです。
- 日中に動くロボ → 社員の操作とバッティングし、データが更新中に上書きされるリスク
- 夜中に通知を飛ばすロボ → 就業時間外の指示になり、就労規則違反になる可能性
- 早朝に動くロボ → 担当者が出社前に必要な情報を揃えられる
これらの条件を踏まえ、「夜間に動かすべき業務」と「朝方に動かすべき業務」を完全に切り分ける運用ルールができました。
夜間に動かすロボの条件
夜間稼働に向いている業務には、いくつかの共通点があります。
| 作業時間が長い | 勤怠移行のように、データ量が多く処理に時間がかかるもの |
|---|---|
| 人間の操作と競合しない | 出退勤中に動かすとデータが変動するため、日中は避ける |
| 通知不要 | 誰かに連絡を飛ばす必要がなく、静かに完了していればOKな作業 |
例:勤怠情報のkintone移行ロボ
→ 作成時間:3〜4時間
→ 完成後は毎日3時間の作業をゼロ化
朝方に動かすロボの条件
朝方稼働に向いている業務には、こちらの特徴があります。
| 情報の鮮度が大事 | 当日朝時点での最新データが必要なもの |
|---|---|
| 人間の判断や対応が直ちに必要 | エラー通知や期限切れ情報など |
| 通知を受け取る人が業務を開始している時間帯 | 就業規則や働き方への配慮 |
例
- 図面提出期限通知ロボ
- 水道承諾書期限通知ロボ
- アルコールチェック未実施者通知ロボ
- 大手ハウスメーカー入退場エラー通知ロボ
- 未確認の受注承認通知ロボ
いずれも作成に3〜4時間かかったが、完成後は毎日数十分〜1時間の短縮を実現。
なぜ時間帯別に分けるのか
時間帯設計の背景には、次のような理由があります。
| 業務の性質に合わせる | 長時間処理系は夜間、対応必須系は朝方 |
|---|---|
| 人間とロボの衝突を避ける | 同時操作でエラーや上書きが起きないように |
| 社員の働き方を守る | 夜中に業務連絡が来ないようにする |
| 翌朝の業務を加速させる | 出社と同時に必要情報が揃っている状態を作る |
この設計思想は、単なる効率化ではなく「社員に優しいDX」というミヨシテックの文化にも直結しています。
時間の再配分で得られたもの
時間帯を意識したロボ運用の結果、ミヨシテックでは次のような変化が起きています。
| 残業時間の減少 | 全館消灯ルールとの相乗効果 |
|---|---|
| 業務の前倒し化 | 午前中に重要タスクが片付くため午後は余裕を持てる |
| 社員のストレス軽減 | 繰り返し作業や期限管理から解放される |
| 新しい業務への着手 | 空いた時間で改善活動や顧客提案が可能に |
この第2章では、「時間帯を意識する」という観点が、ロボパット運用の価値を何倍にも引き上げることをお伝えしました。
次の章では、深夜稼働ロボの具体的な役割と効果について掘り下げていきます。
深夜に動くロボ:静かな時間を最大活用
深夜はロボの独壇場
人がいない夜間は、ロボパットにとってもっとも効率的に働ける時間です。
誰も操作していないためシステム混雑やデータの上書きがなく、長時間かかる処理もじっくり進められます。
ミヨシテックでは、この時間を「静かなゴールデンタイム」と位置づけ、昼間には向かない大規模・長時間処理をロボに任せています。
勤怠情報のkintone移行ロボ
深夜稼働ロボの代表が、勤怠情報をkintone勤怠管理アプリに移す作業です。
以前の状況
- 勤怠管理ソフトにログイン
- 従業員一人ひとりの勤務データを確認(約110人分)
- kintone勤怠管理アプリへ転記
- データ数が多く、人手だと時間も集中力も必要
課題
- 日中は出退勤操作が行われるためデータが変動
- 昼間に処理すると上書きや重複のリスク
解決策
- 夜中にロボがログインし、全社員の勤怠データを一括転記
- 誰も触らない時間に処理することで安全・確実に実行
作成時間とリターン
このロボの作成には約3〜4時間かかりました。
しかし、完成後は毎日3時間分の手作業が完全になくなるため、わずか2日で投資回収が完了します。
「3時間作って、毎日3時間返ってくるなら、作らない理由がない」
これが社内で広まった勤怠ロボの評価です。
夜間稼働のメリット
勤怠ロボ以外にも、夜間に向いている作業は多数あります。
共通するメリットは以下の通りです。
| 処理時間の制限がない | 昼間なら迷惑になる長時間作業も、夜間なら自由に使える |
|---|---|
| 人との操作競合がゼロ | データの更新ミスや中断が起きない |
| 翌朝には結果だけが残る | 社員は到着と同時に完了済みデータを確認できる |
深夜ロボがつくる“前倒しスタート”
この勤怠ロボがあることで、翌朝の総務・経理担当者は勤怠チェックをゼロから始める必要がありません。
結果の確認と例外処理だけに集中でき、始業直後から本来やるべき付加価値の高い業務に着手できます。
深夜ロボは、単に残業を減らすだけでなく、翌日の業務構成を変え、会社全体の時間配分を前倒しにする効果をもたらします。
この第3章では、深夜稼働ロボの代表例である勤怠移行ロボを中心に、その作成背景と投資効果をお伝えしました。
次章では、朝方に動く通知系ロボの役割と効果を解説します。
朝方に動くロボ:今日の業務を先回り
朝に情報がそろっていることの価値
深夜ロボが翌日の業務土台を整える存在だとすれば、朝方ロボは“今日動くための地図”を渡してくれる存在です。
出社した瞬間に、必要な期限情報やエラー通知がそろっている。これによって社員は朝から迷わず優先度の高い仕事に取りかかれます。
ミヨシテックでは、通知系ロボの稼働時間を朝7〜8時に設定。
これは「社員が起きている時間に通知を届ける」ためです。
就業規則に抵触しないよう、夜中に業務指示を飛ばさないという配慮もあります。
図面提出期限通知ロボ
以前の状況
- 事務スタッフが案件ごとに提出期限を確認
- 担当者に個別連絡
- 案件数が増えるとチェックだけで1時間以上かかる
ロボ化後
- kintoneの案件データを参照し、期限が迫った案件を自動抽出
- 担当者ごとに通知を送信
| 作成時間 | 約3時間 |
|---|---|
| 効果 | 毎日約45分削減、5日で回収 |
水道承諾書期限通知ロボ
以前の状況
- 図面と同じく期限管理は手作業
- 細かい日付確認が多く、ミスも発生
ロボ化後
- kintoneのデータをもとに期限が近い案件を通知
| 作成時間 | 約3時間 |
|---|---|
| 効果 | 毎日30〜40分削減、6日で回収 |
前日のアルコールチェック確認ロボ
以前の状況
- アルコールマネージャーのクラウドにアクセスし、前日の結果を確認
- 未実施者がいれば本人と社長へ連絡
ロボ化後
- 自動でデータ取得&未実施者を特定し、本人と社長へ名指し通知
- 社員の意識向上にも直結
| 作成時間 | 約4時間 |
|---|---|
| 効果 | 毎日30分削減+安全管理強化 |
kintoneからANDPADへの案件登録ロボ
以前の状況
- お客様台帳アプリで案件情報を作成後、職人が見るANDPADに手入力
- 二重登録による時間ロス
ロボ化後
- kintoneから必要情報を抽出し、ANDPADに自動登録
- kintoneアカウントがない職人も即時情報共有可能
| 作成時間 | 約4時間 |
|---|---|
| 効果 | 毎日20分削減+情報共有スピード向上 |
大手ハウスメーカー入退場エラー通知ロボ
以前の状況
- 女性スタッフが入退場管理アプリを手動で確認
- エラーがあればハウスメーカーに連絡
ロボ化後
- 自動でエラー検出し、担当者に通知
| 作成時間 | 約3時間 |
|---|---|
| 効果 | 毎日30分削減、6日で回収 |
未確認の受注承認通知ロボ
以前の状況
- 受注承認が止まっている案件を手動確認
- 承認遅延による工期遅れリスク
ロボ化後
- 承認が滞っている案件を自動検出し、担当者へ即通知
| 作成時間 | 約3時間 |
|---|---|
| 効果 | 毎日20分削減+遅延リスク回避 |
通知系ロボの共通メリット
| 期限管理の精度向上 | 人の見落としをゼロ化 |
|---|---|
| 情報伝達の迅速化 | 朝イチで全員に必要情報が行き渡る |
| 心理的負担の軽減 | 期限やエラー確認のプレッシャーから解放 |
| 作成時間の短期回収 | ほぼ1週間以内に投資回収 |
“作成に時間がかかる”ではなく“すぐ元が取れる”
6種類の通知系ロボを作るのにかかった合計時間は約20時間。
一見大きな時間投資に見えますが、全ロボの効果を合算すると1日あたり約3時間削減、7日以内にすべての元が取れる計算です。
つまり、この20時間は「未来の数百時間」を買ったことになります。
次の第5章では、これら深夜・朝方ロボの作成時間がどのように“未来の時間”として返ってくるのか、時間口座の視点で具体的に掘り下げていきます。
作成時間=未来の“時間口座”への貯金
時間を“お金”のように管理する発想
ミヨシテックでは、RPAロボパットで作業を自動化することを「時間口座に貯金する」と表現しています。
ロボを作るときに必要な作成時間は“元手”であり、稼働するたびに返ってくる時間は“利息”です。
| 元手(作成時間) | ロボを作るために最初にかける3〜4時間 |
|---|---|
| 利息(効果時間) | ロボが動くたびに浮く数十分〜数時間 |
| 運用期間 | 条件が変わらない限り、毎日稼働し続ける |
この考え方だと、ロボ作成時間は単なるコストではなく、未来にわたって利益を生み続ける投資として捉えられます。
投資回収の計算例
実際のロボを例に、投資回収までの日数を計算してみます。
勤怠移行ロボ
| 作成時間 | 4時間 |
|---|---|
| 1日あたり削減時間 | 約3時間 |
| 回収日数 | 約2日 |
図面提出期限通知ロボ
| 作成時間 | 3時間 |
|---|---|
| 1日あたり削減時間 | 約45分 |
| 回収日数 | 約4日 |
水道承諾書期限通知ロボ
| 作成時間 | 3時間 |
|---|---|
| 1日あたり削減時間 | 約35分 |
| 回収日数 | 約5日 |
アルコールチェック確認ロボ
| 作成時間 | 4時間 |
|---|---|
| 1日あたり削減時間 | 約30分 |
| 回収日数 | 約8日 |
ANDPAD登録ロボ
| 作成時間 | 4時間 |
|---|---|
| 1日あたり削減時間 | 約20分 |
| 回収日数 | 約12日 |
入退場エラー通知ロボ
| 作成時間 | 3時間 |
|---|---|
| 1日あたり削減時間 | 約30分 |
| 回収日数 | 約6日 |
受注承認通知ロボ
| 作成時間 | 3時間 |
|---|---|
| 1日あたり削減時間 | 約20分 |
| 回収日数 | 約9日 |
合計で見るとすごい数字になる
個別のロボごとの効果も大きいですが、全ロボの効果を合算するとさらにインパクトが増します。
| 合計作成時間 | 約24時間(3営業日分) |
|---|---|
| 合計削減時間 | 1日あたり約5時間 |
| 投資回収期間 | わずか5日 |
つまり、1週間以内に元が取れ、その後はずっと利益(時間)を生み続けることになります。
このあと第6章で、これらのロボ活用が会社文化や社員の意識をどう変えたかにフォーカスします。
文化への影響と運用のコツ
残業が減っただけではない変化
ロボパット導入の効果は、「残業削減」という分かりやすい数字の改善だけにとどまりません。
ミヨシテックでは、時間帯別に動くロボの存在が、職場全体の空気感や社員の意識を変えていきました。
| “ロボがやってくれる”安心感 | → 単純作業を忘れたらどうしようという不安から解放 |
|---|---|
| 業務開始時点で“整った状態”から始められる快適さ | → 朝からエンジン全開で動ける |
| 空いた時間を活かす意識の芽生え | → 削減された時間を新しい挑戦に充てる習慣が定着 |
「この作業もロボ化できる?」という発想が広がる
ロボパットの効果を目の当たりにした社員から、自然と次のような声が増えました。
- 「このエクセルの集計も自動でできませんか?」
- 「この入力作業も夜間ロボにやらせたい」
- 「このチェック業務も通知にできるのでは?」
これらは単なる思いつきではなく、“業務の自動化を前提に考える文化”が社内に根付いた証拠です。
残業ゼロを支える仕組みとの相乗効果
もともとミヨシテックには20:00全館消灯ルールがあり、物理的に残業を防ぐ仕組みがありました。
しかし、消灯ルールだけでは「終わらない仕事」が存在すれば結局持ち帰りや休日作業が発生します。
RPAによる自動化と全館消灯ルールを組み合わせることで、業務量そのものを減らし、物理的・実務的の両面から残業を防ぐことが可能になりました。
運用を長く続けるためのコツ
ロボは作って終わりではなく、動かし続けることで価値を発揮します。
ミヨシテックでは、次のような工夫をしています。
| エラー検知と迅速対応 | ロボが止まったらすぐ気づける通知設定を導入 |
|---|---|
| 業務フロー変更時の即修正 | システムや手順が変わったらロボもすぐ改修 |
| 小規模改良を積み重ねる | 「ついでにここも自動化」精神で日々改善 |
| 成果の見える化 | 削減時間や回収日数を社内で共有し、モチベーションを維持 |
月1回の「ロボパットマスター会」で知識を共有
さらに、運用の質を高め続けるために、月1回「ロボパットマスター会」を開催しています。
この会は、ロボパットマスター認定を受けた社員が集まり、次のような活動を行います。
- 各自が作成したロボットの発表
- 作りたいロボのアイデア共有
- 「こんなロボット作れるかな?」という相談
- 部署をまたいだ意見交換・解決策の検討
発表された内容は、他部署でも応用できるノウハウとして活かされることが多く、相談から新たなロボが誕生するケースも珍しくありません。
こうした場があることで、RPA活用が“個人技”ではなく全社的なチーム戦になっています。
ロボは“時間を生み続ける社員”である
社員一人ひとりが担当業務を持っているように、ロボもそれぞれ担当業務を持っています。
違うのは、人間は勤務時間に制限がありますが、ロボは24時間いつでも動けるという点です。
- 夜間は大量データの移行
- 朝方は通知やエラー報告
- 必要なら休日も稼働可能
この“時間無制限の社員”が複数いることが、会社全体の余裕を生み出しています。
文化ごと変えるRPA活用
ミヨシテックが行ったのは、単にRPAを導入しただけではありません。
動かす時間の最適化+作成時間を投資と捉える発想+知識共有の場が、業務の進め方、社員の意識、職場の文化そのものを変えました。
結果として、
- 残業の大幅削減
- 業務の前倒し化
- 新しい挑戦への時間創出
- 自動化を前提に考える文化の定着
- 全社的なナレッジ共有によるロボの進化
これらすべてが同時に実現し、今も進化を続けています。
“動く時間”まで設計するRPA活用が会社を変える
ミヨシテックのロボパット活用は、単に手作業を自動化するだけではありません。
「いつ動かすか」まで設計する運用と、作成時間を投資として捉える発想が大きな成果を生みました。
- 夜間ロボで誰もいない間に大量処理を完了
- 朝方ロボで始業と同時に必要な情報を揃える
- 各ロボ作成にかかった3〜4時間は、数日〜数週間で回収
- 全館消灯ルールとの組み合わせで残業ゼロに近づく
- 月1回のロボパットマスター会でナレッジを共有し、全社的に進化
この結果、残業削減・業務前倒し・社員の意識改革という3つの変化が同時に実現しました。
投資は「時間」で返ってくる
1つのロボを作る時間は、未来の自分たちへのプレゼントです。
作成したその日から、ロボは毎日欠かさず時間を生み出し続けます。
そして、その時間は新しい業務・顧客対応・改善活動といった“攻めの仕事”に使えるようになります。
自動化はゴールではなく、文化のスタート
ロボパットが本領を発揮するのは、導入した瞬間ではありません。
運用し、改善し、全社でノウハウを共有する。このサイクルを回し続けることで、“自動化が当たり前”という文化が育ちます。
最後に
ミヨシテックでは、今回ご紹介したようなロボパット活用のノウハウをそのまま活かした導入支援を行っています。
初期設定やロボ作成のサポートはもちろん、導入後も月1回のサポートミーティングで、運用の疑問や新しいロボの相談にお応えします。
さらに、1か月無料トライアルもご用意。
会社見学会では、ロボパットを実際に触っていただける体験会も開催していますので、「まずは試してみたい」「うちの業務でもできる?」というご相談だけでも歓迎です。
ロボパットで“時間の使い方”が変わる瞬間を、ぜひ一度体感してください。