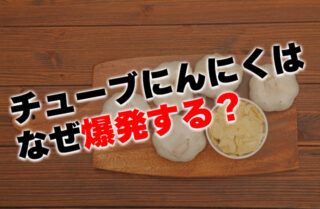PC嫌いな現場にDXが根づいた、ミヨシテックの本気
2025.08.06
PC苦手な現場で、なぜクラウドは嫌われたのか
「なんでこんなん使わなあかんねん」
これは、クラウドサービス導入初期のミヨシテック現場で何度も聞こえてきた声です。導入されたクラウドツールは、施工管理の効率化を目的に選ばれたもので、現場の進捗報告や写真の共有、図面確認などがオンラインで完結するはずでした。しかし、実際に運用を始めてみると、現場の空気は冷え切っていました。
「紙でええがな」「スマホで図面なんか見づらい」「どこに保存されてるかわからん」「そもそもログインできへん」
そんな声が次々と上がりました。
もともとミヨシテックは、ベテラン職人が多く在籍する技術集団です。彼らにとって、現場に必要な情報は紙の図面とホワイトボード、そして電話でのやりとりが基本でした。手に馴染んだそのやり方は、長年の経験と工夫の積み重ねでもありました。そこに突然、「クラウドを使え」と言われても、すんなり馴染むはずがありませんでした。
加えて、「PCが苦手」という背景も大きな要因でした。文字入力ひとつ取っても、「キーボードを打つより、紙に書くほうが早い」というのが現場のリアルな感覚です。普段はパソコンどころか、スマホのアプリすらまともに使わない職人たちにとって、“クラウドサービス”はあまりにもハードルが高かったのです。
そして忘れてはならないのが、時間のなさです。現場の朝は早く、日中は移動と作業の連続です。事務所に戻るのは夕方以降という日も多く、そんな中で「ツールの操作を覚えておいてください」と言われても、学ぶ余裕はありませんでした。「覚える時間がない」「教えてくれる人がいない」「そもそも必要性がわからない」。
導入を阻む三重苦がのしかかっていたのです。
さらに、最も大きな障壁となったのが“実感のなさ”でした。部分的な最適化(効率化)では会社全体の改善に至らないと考え、「全体最適」を意識したシステム構築を進めていたため、現場側のメンバーには具体的に「自分の仕事がどう楽になるのか」は伝わりにくかったのです。その結果、「これからはこれでいきます」と言われても、当然のように拒否反応が起きました。
こうして、せっかく導入したクラウドツールは、まともに使われることなく「不便なもの」として現場に嫌われ、やがて“形だけの運用”に変わっていきました。現場に配られたタブレットは、使われることもなく机の上に放置され、図面は結局、事務所で印刷された紙を持っていくという元のスタイルに戻っていきました。
そのうちに、クラウドは“やらされ感”の象徴となり、ツールを開くだけで気が重くなる…という職人もいたほどです。
このときの失敗は、後のkintone導入にも大きく影響しました。
現場には、環境の変化=めんどくさい・難しい・いらんこと、という苦い記憶が残ってしまっていたのです。
この「過去の失敗体験」をどう乗り越えるか。それが、ミヨシテックのDXが再び動き出すうえで、最大の課題となりました。
kintone導入、ブルドーザー社長の独断と突破
クラウド導入の失敗で現場に残ったのは、「デジタルはめんどくさい」という強烈な負の印象でした。
その空気を一変させたのが、私たちのブルドーザー社長です。
社長は、ある日こう言い放ちました。
「もう紙のやり方に戻るのはやめます。これからはデジタルでいきます。うちの会社の未来はそこにしかありません!」
現場からは当然、ため息とブーイングの嵐です。
「またかいな」「前ので懲りたやろ」「紙で十分や」。
そんな声が飛び交いましたが、社長は一切引きませんでした。
あだ名の通り、ブルドーザーのように障害物を押しのけてでも進む人だったのです。
次なる武器として選ばれたのが「kintone」でした。
kintoneは、クラウド上でデータベース型のアプリを自由に作れるツールです。
とはいえ、当初の現場の反応は予想どおり冷ややかでした。
「前の自社専用ソフトで散々やったのに、また新しい管理環境か…」
「結局、誰が作るねん?また現場に丸投げちゃうんか?」
ここで重要な役割を果たしたのが、社内で名の知れたシステム課の藤原です。
藤原は、まずは簡単なアプリを自作し、現場に試してもらうところから始めました。
「最初はマニュアルを作らず、直感で触って覚えてもらう」という方針でした。
しかし、現場の反応は冷たかったのです。
「なんやこれ、前よりやりにくいやん」
「また覚えなあかんのか」
「誰がこんなんやるねん」
正直なところ、kintoneの最初の数週間は前回のクラウド以上に評判が悪かったです。
システム課が一生懸命作ったアプリも、ほとんど開かれない日が続きました。
しかし、ここでブルドーザー社長が動きました。
「まずは簡単なことだけでいい。慣れたら次に進めばいい」と方針を転換したのです。
一気にすべてをデジタル化するのではなく、まずは“毎日の活動履歴を残すだけ”のアプリに絞りました。
さらに、ここからが社長らしい戦略でした。
月1回の点検評価に、このアプリの入力状況を紐付けたのです。
つまり、入力していないと評価が下がり、昇給や賞与にも影響する仕組みを作りました。
現場からは「なんちゅうやり方や」「脅しやんか」と不満の声も出ましたが、ルールはルールです。
誰もがいやいやながらも、毎日kintoneを触るようになりました。
すると、人間というのは面白いもので、毎日のことになると自然と操作に慣れてきます。
最初は文句しか言わなかった職人たちも、いつの間にかこう言い始めました。
「これ、もっとこうできひんか?」
「写真も一緒に残せたら便利やな」
「せっかくやから、次は図面も見れるようにしてほしいわ」
あれだけ拒否していた現場から、改善要望やアイデアが出始めた瞬間でした。
ここから、ミヨシテックのkintone活用は一気に加速していくことになったのです。
女性社員の活躍とアプリ開発体制
kintoneが少しずつ現場に浸透し始めると、次に社内で動き出したのは女性社員の存在でした。
ミヨシテックには、各部署に必ず事務やサポートを担う女性社員が在籍しています。
彼女たちは、日ごろから伝票整理や顧客対応などを通じて、業務の流れを一番よく把握している存在です。
そして何より、新しいことを学ぶことに抵抗が少なく、デジタルへの順応も早かったのです。
社内では、kintoneアプリを自由に作れるわけではありません。
以前のコラムでも触れましたが、簡単な社内研修を受講した人だけがアプリ作成を担当できるというルールがありました。
これは、誰でも好きに作ってしまうと情報が散らばり、かえって混乱を招く恐れがあるからです。
このルールの下、各部署で1人ずつ、女性社員がkintoneの“アプリクリエイター”として育成されました。
最初は「私にできるかな…」と不安そうにしていた社員も、研修を受けてみると
「思ったより簡単そう!」「こういう考え方ができるとアプリ作成までの構成もスムーズにできそう!」と前向きになっていきました。
女性社員の強みは、現場と事務の間に立っていることです。
現場で必要な情報と、事務所でまとめるべき情報、その両方を理解しているため、アプリ設計のポイントをすぐに掴めます。
例えば、作業日報アプリであれば「現場が入力しやすい最低限の項目だけ」にしつつ、事務処理に必要な情報は自動集計できるように工夫する、といった具合です。
こうして、現場の不満を吸い上げながらも、アプリの作り込みは女性社員が中心となって進みました。
彼女たちは、ただ作るだけでなく、現場に説明して使い方をサポートする役割も果たしました。
「ここはこう押すだけですよ」「写真はここから添付できます」
そんな何気ない一言が、現場の抵抗感を和らげていったのです。
この取り組みが功を奏し、社内では次々と部署ごとのオリジナルアプリが生まれました。
点検管理アプリ、材料発注アプリ、修理履歴アプリ…。
現場の声を反映させながら改良を重ねるうちに、アプリの数はみるみる増えていきました。
やがて、その数は約700個に到達します。
しかも驚くべきことに、ほとんどのアプリが実際に使われ続けていました。
「次はこんな情報も入れたい」「このアプリにこの機能つけられへん?」
そんな声が現場から上がるようになったのです。
最初は「なんでこんなん使わなあかんねん」と言っていた職人たちが、
自らアイデアを出すようになる。これはまさに社内DXが根付いた証拠でした。
一方で、アプリが増えたことによる新たな課題も生まれます。
項目が増えすぎて操作が複雑になり、不慣れな社員はついていけなくなりかけたのです。
700個のアプリと“欲望の連鎖”
現場と女性社員の二人三脚で進めてきたkintone活用は、ついに社内で大きな成果を見せ始めました。
最初は1つの活動履歴アプリからスタートした取り組みが、やがて部署ごとに独自のアプリ開発へと広がっていったのです。
「材料の発注をもっと簡単にしたい」
「点検記録を紙に書くのはもうやめたい」
「現場の写真をまとめて残せたら便利やな」
現場からの声に応える形で、次々と新しいアプリが生まれました。
最初は数個だったアプリが、10個、50個、100個と増えていき、気がつけば約700個に達していました。
この数字は、単なる勢いではありません。ほとんどのアプリが、日常業務の中で実際に使われ続けていたのです。
現場では、アプリの便利さを実感するたびに新たな要望が出てきました。
「次は、こんな機能もあったら助かるんやけど」
「この情報もついでに入れといてくれたら、事務所の仕事が楽になるで」
こうした声は、やがて“欲望の連鎖”を生み出しました。
最初は「いやいや触るだけ」だった職人たちが、いつしか主体的に改善提案を出すようになったのです。
その変化は、まさに社内DXが文化として根付き始めた証でした。
しかし、アプリが増えれば増えるほど、新たな課題も浮かび上がります。
一つは情報の複雑化です。便利にしようと項目を足していくうちに、アプリの入力画面が長くなりすぎてしまうことがありました。
特にデジタルが得意でない社員にとっては、「どこに何を入れたらいいのか」がわかりにくくなってしまったのです。
もう一つは運用の属人化です。アプリの作成や更新は研修を受けた社員が中心となっていましたが、高度な設定になるとシステム課に頼る場面が増えました。
結果として「このアプリ、作った本人しか細かいことがわからない」という状態が起きかけたのです。
便利さを求めて進化してきたはずのkintone運用が、逆に情報過多と複雑化によって、一部の社員には「また難しくなったな…」と感じられ始めていました。
そこでミヨシテックは、次のステージとして全体の再構築に踏み切ります。
アプリを整理し、シンプルで直感的に操作できる形に整え直す取り組みです。
これは単なる整理作業ではありません。現場の声を聞きながら、「本当に必要な情報は何か」「どの画面なら誰でも迷わず使えるか」を改めて洗い出す作業でした。
700個のアプリは、ミヨシテックの成長の証であると同時に、DXは“作って終わり”ではなく“使われ続けて初めて価値になる”ことを示す象徴でもありました。今まさに私たちは、さらなる改善に向けて現場と共に進化を続けています。この取り組みが会社全体の文化を変え、次の未来につながっていくのです。
DXは現場と共に進化する
ミヨシテックのDXの歩みを振り返ると、最初は現場からの強烈な反発から始まりました。「なんでこんなん使わなあかんねん」「紙でええがな」という声が飛び交い、初めて導入したクラウドツールはほとんど使われないまま終わりました。しかし、ブルドーザー社長の決断とシステム課藤原の試行錯誤、そして女性社員を中心とした社内サポートの努力によって、少しずつ状況は変わっていきました。
最初はいやいや触っていたkintoneも、毎日の入力が習慣になることで自然と慣れが生まれました。やがて職人たち自身から「もっとこうできひんか?」と改善の声が上がるようになり、社内には次々と新しいアプリが誕生しました。こうして生まれた約700個のアプリは、単なる業務ツールではなく、現場と会社をつなぐ“情報の血流”となったのです。
この過程を通じて私たちが学んだことは、DXはツールを導入しただけでは成功しないということです。大切なのは、人が慣れ、文化として根付くまで寄り添い続けることです。強制から始まった取り組みも、現場の声を聞き、改善を重ねることで「自分たちの便利な仕組み」へと変わりました。DXは技術の話ではなく、人と現場の物語なのだと強く実感しています。
そして、この取り組みは現在進行形で進化を続けています。私たちは今もアプリの整理や改善を行い、よりシンプルで使いやすい形へと磨き上げています。DXは一度完成したら終わりではありません。現場と共に成長し、会社全体を支える仕組みとして息づいていくものです。
非IT人材で成果が出る DX成功ルール
このリアルな経験と具体的なノウハウをまとめたのが、書籍『非IT人材で成果が出る DX成功ルール』です。現場の反発をどう乗り越えたか、どのように社内に文化を根付かせたか、そして失敗から得た学びまで余すことなく記しています。DXに悩む中小企業の方や、社内で変革を起こしたいと考える方には、きっとヒントになるはずです。
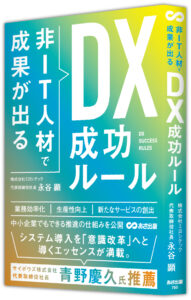
ミヨシテックのDXは、まだ終わりではありません。現場の声に耳を傾け、挑戦を続ける限り、私たちのDXは進化し続けます。そしてその一歩一歩が、会社を強くし、働く人を幸せにする原動力になるのです。