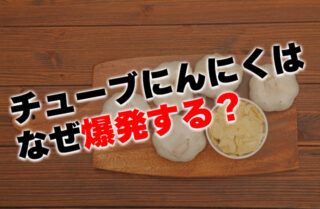レーダー探査とX線探査を徹底比較!失敗しないコンクリート内部調査の選び方
2025.09.13
はじめに
マンションやオフィスビル、学校や工場などの建物は、長く使っていくうちに空調や配管、電気設備の更新や増設が必要になります。そのとき必ずといっていいほど出てくるのが「壁や床に穴をあける工事(穿孔工事)」です。
一見シンプルに思えるこの作業ですが、実は注意が必要です。コンクリートの内部には鉄筋や電気の配線、水道管などが埋め込まれており、もし誤って切ってしまうと建物の強度が弱まったり、停電や漏水といったトラブルにつながってしまいます。修復には大きな費用や時間がかかることもあり、施工する側にとっても利用者にとっても大きな負担になりかねません。
こうしたリスクを避けるために活躍するのが「非破壊検査」と呼ばれる調査方法です。コンクリートを壊さずに中の様子を確認できるもので、代表的なのが レーダー探査 と X線探査。それぞれに得意・不得意があり、現場の条件によって使い分けることが大切です。
今回のコラムでは、レーダー探査とX線探査の違いをわかりやすく解説するとともに、実際の施工事例を交えながら「どんな場面にどちらが適しているのか」をご紹介します。
レーダー探査とは
コンクリートの中を調べる方法のひとつに「レーダー探査」があります。仕組みはシンプルで、コンクリート表面から電磁波を発射し、その反射を捉えることで内部にある物体の位置を推定します。イメージとしては、地面に向けて電波を送って地下の様子を探る「地中レーダー」と似ています。
レーダー探査の大きな特徴は、スピーディーに広範囲を調査できることです。専用の探査機を床や壁に沿って動かすだけで、リアルタイムにモニターへ結果が表示されます。そのため、短時間で多くの場所を調べたい現場や、工期に余裕がない工事では重宝されます。
また、電磁波を使うため、放射線のような特別な管理は必要ありません。第三者が近くにいても安全で、調査区域を大きく制限しなくてよいのもメリットのひとつです。建物が稼働中で人の出入りが多いオフィスや商業施設などでは、レーダー探査の安全性が大きな利点になります。
一方で、弱点もあります。レーダー探査は水分や鉄筋が密集した部分で誤差が生じやすく、内部の配管や鉄筋の「正確な太さ」や「切断してよいかどうか」まで判断するのは難しいのです。おおまかな位置を把握するには便利ですが、精密な施工が求められる場合には限界があるといえるでしょう。
つまりレーダー探査は、
- 広い範囲を素早く調べたい
- 安全性を優先したい
- おおまかな埋設物の位置を知りたい
といった現場で効果を発揮します。
次章では、より精度の高い調査方法である「X線探査」について解説します。
X線探査とは
もう一つの代表的な非破壊検査が「X線探査」です。名前の通り、病院で受けるレントゲン撮影と同じ仕組みで、コンクリートにX線を照射し、その透過画像をもとに内部の状況を調べます。
X線探査の最大の特長は、精度の高さです。レーダー探査では「おおよその位置」を把握するのが得意でしたが、X線探査は鉄筋の正確な位置や太さまで確認できます。これにより、「強度を損なわない範囲で鉄筋を避けて穴をあけられるか」「鉄筋を切断しても安全か」といった判断が可能になります。穿孔工事やアンカー工事など、ミリ単位の精度が求められる現場では欠かせない調査方法です。
さらに、配管や電線などの埋設物の位置をより明確に映し出せるため、誤って破損するリスクを大きく減らせます。もし病院や学校などで電気ケーブルを切断してしまうと、停電や通信障害に直結します。こうした重大トラブルを防げるのもX線探査の大きなメリットといえるでしょう。
一方で、X線探査にも注意点があります。放射線を利用するため、撮影の際は安全管理が必須です。作業場所から半径5メートルを立入禁止にし、有資格者が放射線量を管理しながら調査を行います。そのため、レーダー探査と比べると作業手順はやや複雑で、コストも高くなる傾向があります。また、対応できるコンクリートの厚さはおよそ30cmまでが目安で、それ以上の厚みでは透過が難しい場合もあります。
とはいえ、建物の強度や利用者の安全を第一に考えれば、「精度を重視すべき現場」ではX線探査が選ばれます。特に学校や病院、工場など、人や設備への影響が大きい施設では、多少コストがかかってもX線探査による調査が有効です。
次章では、レーダー探査とX線探査を項目ごとに比較し、それぞれの違いを整理してみましょう。
レーダー探査とX線探査の比較
ここまで、レーダー探査とX線探査の特徴をそれぞれ見てきました。どちらも「コンクリート内部を壊さずに確認できる」という点では共通していますが、実際の現場で選ぶ際には違いをしっかり理解しておくことが大切です。ここでは、代表的な比較ポイントを整理してみましょう。
精度
レーダー探査
鉄筋や配管の「おおまかな位置」を知るのに適しています。ただし、鉄筋が密集している場所や、水分を多く含む場所では反射波が乱れやすく、正確な判定が難しくなる場合があります。
X線探査
鉄筋の位置や太さまで高精度に判別可能。切断しても強度的に問題がないかどうかの判断材料にもなり、ミリ単位の施工が求められる現場で有効です。
コスト
レーダー探査
比較的安価で、短時間に広い範囲を調査できるため、費用対効果に優れます。
X線探査
放射線管理のための体制や撮影準備が必要なこともあり、レーダーより費用がかかる傾向があります。ただし「調査精度によって得られる安心感」を考えると、無駄な補修工事を防げる点でトータルコストは抑えられることもあります。
対応できる厚さ
レーダー探査
コンクリートの厚さ15cm程度まで対応可能。比較的厚い構造物の調査にも有効です。
X線探査
およそ30cm程度が目安。厚みがある場合は透過が難しいケースも出てきます。
安全性
レーダー探査
電磁波を使用するため放射線の心配はなく、第三者が近くにいても安全に作業できます。稼働中の建物や人通りの多い現場に適しています。
X線探査
放射線を使用するため、撮影中は半径5mを立入禁止にするなど安全管理が必須。有資格者が線量管理を行う必要があります。
作業スピード
レーダー探査
リアルタイムで結果が表示されるため、調査後すぐに判断が可能。短時間で複数箇所を調べられます。
X線探査
撮影や画像確認に一定の時間がかかりますが、精度の高いデータを得られる点で信頼性があります。
適した現場
レーダー探査
概略を把握すれば十分な調査や、短期間で広範囲を確認したい場合に有効。人の出入りが多い建物でも制限が少なく実施可能。
X線探査
精密な穿孔工事やアンカー施工が必要な場面、鉄筋切断の可否を判断したい現場、失敗が許されない病院・学校・工場などに最適。
このように、レーダー探査とX線探査は「スピードと手軽さを重視するのか」「精度を重視するのか」で選び方が変わります。次章では、実際にどんな現場でどちらを選ぶべきなのかを、より具体的に見ていきましょう。
どんな現場でどちらを選ぶべきか
レーダー探査とX線探査にはそれぞれの強みがあります。では実際の現場では、どのように選び分ければ良いのでしょうか。ここでは代表的なケースを取り上げながら解説していきます。
レーダー探査が向いている現場
-
広い範囲を短時間で調べたい場合
ショッピングモールやオフィスビルなど、複数箇所の調査が必要なときにはスピードが重要です。レーダー探査ならリアルタイムで結果が得られるため、効率的に広い面積をカバーできます。
-
人の出入りが多い場所での工事
レーダー探査は電磁波を使うため、安全管理上の制約が少なく、稼働中の施設や人通りのある現場でも調査が可能です。業務を止められない店舗や病院の共用部などでは特にメリットが大きいです。
-
概略の把握で十分なケース
「このエリアにどの程度鉄筋が入っているか」「配管の有無を大まかに知りたい」といった、施工前の一次調査や計画段階での調査にはレーダー探査が適しています。
X線探査が向いている現場
-
穿孔やアンカー施工で正確な位置が必要な場合
空調設備や配管を通すための穴あけ工事では、鉄筋や配管を避けながら施工しなければなりません。X線探査なら鉄筋の位置や太さを正確に確認できるため、施工の安全性が高まります。
-
鉄筋の切断可否を判断する必要がある場合
改修工事の中には、強度的に問題がない範囲で鉄筋を切断する必要があるケースもあります。その際に役立つのがX線探査です。鉄筋径まで把握できるため、設計者や施工者が安心して判断できます。
-
失敗が許されない施設での工事
病院や学校、工場など、もし電気配線や配管を損傷してしまうと大きな影響が出る施設では、多少コストや手間がかかっても精度を優先すべきです。人命や事業活動に直結する建物では、X線探査の選択が安心につながります。
実際の現場判断のポイント
| 調査範囲の広さ | 広ければレーダー探査が有利。 |
|---|---|
| 必要な精度 | 高精度が求められるならX線探査が必須。 |
| 周囲環境 | 稼働中の施設や人通りが多い場合はレーダー、制限を設けられる現場ならX線。 |
| 予算と工期 | 短工期・低コストならレーダー、長期的な安心を重視するならX線。 |
まとめると、レーダー探査は「スピードと安全性」、X線探査は「精度と信頼性」が強みです。工事の内容や現場環境によって使い分けることが理想ですが、実際には「最終的な穿孔やアンカー工事の前にはX線探査を実施する」という流れが多く見られます。
次章では、ミヨシテックが提供しているX線探査の強みについて、具体的にご紹介します。
ミヨシテックが提供するX線探査の強み
ミヨシテックでは、関西を中心に数多くの現場でX線内部探査を行ってきました。穿孔工事やアンカー工事を安全に進めるためには、精度と信頼性の高い調査が欠かせません。ここでは、当社が提供するX線探査の特長を整理してご紹介します。
① 現場で即時確認が可能
従来のX線探査では、フィルム現像に時間がかかることもありました。しかしミヨシテックではデジタル方式を採用しており、撮影した画像をその場でPCモニターに映し出せます。施工担当者と調査員が一緒に画面を見ながら判断できるため、「ここに穴をあけても大丈夫か」を即座に確認でき、工事の効率化にもつながります。
② 高精度な探査
X線はコンクリート内部を透過するため、鉄筋の配置や太さ、配管やケーブルの位置を鮮明に映し出せます。これにより、鉄筋を切断しても強度的に問題がないかどうかの判断が可能です。ミリ単位の精度が必要なアンカー工事や設備更新工事でも、安心して施工を進められます。
③ 徹底した安全管理
X線を使用するため、撮影時は労働安全衛生法や電離放射線障害防止規則に基づいて、安全を最優先に管理しています。撮影範囲は半径5メートルを立入禁止に設定し、有資格者が線量計を使って放射線を常時管理。さらに第三者が誤って立ち入らないよう、必ず監視員を配置しています。工事現場で働く方はもちろん、周囲の方々の安全も確実に守る体制を整えています。
④ 画像データの提供
調査で撮影したレントゲン画像は、JPGやPDF形式でデータとして提供しています。これにより、施工後の記録として保存したり、設計者や管理者と情報共有したりするのが容易になります。後から確認したいときや、竣工書類に添付したいときにも役立ちます。
⑤ 幅広い実績と対応力
学校や病院、公共施設はもちろん、工場やオフィスビルなど多種多様な建物での施工実績があります。高所作業車を用いた工場での探査や、夜間に行う病院での工事など、現場ごとの制約に応じた柔軟な対応が可能です。関西一円を中心に、遠方への対応もご相談いただけます。
このように、ミヨシテックのX線探査は「即時確認」「高精度」「安全管理」「データ提供」「豊富な実績」という5つの強みで、多くのお客様にご安心いただいています。次章では、実際に工場で行った施工事例を具体的にご紹介します。
【施工事例紹介】工場でのX線探査
ここからは、実際にミヨシテックが行った工場でのX線探査の事例をご紹介します。いずれも「鉄筋や配管を損傷させずに安全に穿孔したい」というニーズからご依頼いただいたものです。現場ごとの条件に合わせて探査を行うことで、工事をスムーズかつ確実に進めることができました。
門真市工場様 X線内部探査
工場内に新しく空調配管を設置するため、コンクリート壁に穿孔が必要となりました。高所での作業だったため、高所作業車を使用しながら探査を実施。X線によって鉄筋や埋設管の位置を事前に確認し、障害物を避けて安全に穴をあけることができました。
施工内容:X線内部探査
施工期間:1日
門真市工場様 X線内部調査
こちらの現場では、衛生配管を新設するにあたり3階外壁に穿孔を行う必要がありました。X線探査で鉄筋や配管の正確な位置を把握したうえで作業を実施。埋設物を損傷することなく、計画通りの位置に穴を開けることができました。
施工内容:X線内部調査
施工期間:1日
大阪市工場様 X線内部探査
工場の空調設備を更新する工事に伴い、コンクリート壁への穿孔が求められました。事前のX線探査で、穿孔予定箇所に鉄筋があることが判明。そこで施工位置を変更し、建物の強度や内部配管に影響を与えることなく作業を完了しました。
施工内容:X線内部探査
施工期間:1日
これらの事例からも分かるように、X線探査を行うことで鉄筋や配管を切断するリスクを回避でき、安全で確実な施工が可能となります。特に工場のように設備や機械が密集している環境では、一度のトラブルが大きな損失につながるため、事前調査の重要性は非常に高いといえるでしょう。
次章では、本コラムのまとめとして、レーダー探査とX線探査の違いを振り返りながら、ミヨシテックの強みを改めてお伝えします。
まとめ
コンクリート内部の非破壊検査には、大きく分けて「レーダー探査」と「X線探査」の2つの方法があります。レーダー探査はスピードや手軽さに優れており、広範囲を短時間で調査したい場合に向いています。一方で、X線探査は鉄筋や配管の正確な位置や太さまで把握できるため、精度を求められる穿孔工事やアンカー工事に欠かせない調査方法です。
今回ご紹介した工場での施工事例からも分かるように、X線探査を行うことで鉄筋や配管を損傷することなく、安全に工事を進めることができます。特に工場・学校・病院など、トラブルが直接業務や安全に影響する建物では、信頼できる非破壊検査が不可欠です。
ミヨシテックのX線探査は、現場で即時確認ができるデジタル方式を採用し、高精度で安全管理を徹底。さらに、施工後の記録として活用できる画像データの提供も行っています。関西エリアを中心に豊富な施工実績があり、工場や公共施設など幅広い現場で安心してお任せいただけます。
穿孔工事や設備改修を控えていて「鉄筋や配管を傷つけないか不安」「どちらの調査方法を選べばいいかわからない」という方は、ぜひ一度ミヨシテックへご相談ください。精度の高いX線探査で、安全で効率的な工事をサポートいたします。