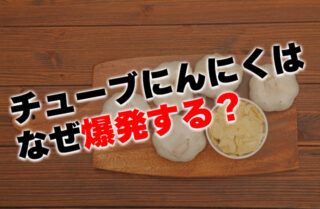体育館にエアコンは必要?設置率22.7%が示す学校空調の現実【文科省調査】
2025.11.27
「暑すぎる体育館」は、もう限界?

真夏の体育館。
外気温が35℃を超える日、屋根の下はまるでサウナのような熱気に包まれます。
床に立っているだけで汗が噴き出し、体育の授業では子どもたちが顔を真っ赤にして息を切らす――。
そんな光景、誰もが一度は見たことがあるのではないでしょうか。
部活動や全校集会、地域の催し物など、体育館は日常的に多くの人が集まる場所です。
しかし、ここ数年の猛暑は従来の「我慢で乗り切る」感覚をはるかに超えています。
特に屋内での熱中症搬送が全国的に増加し、体育館での活動を一時中止する学校も出てきました。
さらに、体育館は災害時の避難所としての役割も担っています。
もし真夏の停電や断水時に、冷房のない密閉空間で多数の避難者が長時間滞在することを想像してみてください。
高齢者や乳幼児にとっては、命に関わる環境です。
こうした背景を受け、全国各地で「体育館にも空調を」という声が高まっています。
しかし、最新の文部科学省の調査によると――
公立小中学校の体育館等の空調設置率はわずか22.7%(令和7年5月1日時点)。
まだ4校に1校も設置されていない現実があります。
これほどまでに暑さが深刻化しているにもかかわらず、なぜ空調の導入が進まない学校が多いのか?
そして、体育館に空調を入れることは本当に必要なのか?
本記事では、その理由と背景、そして導入のメリットや実現のポイントを、専門的な視点から解説します。
現状 ― 体育館の空調設置率はわずか22.7%
文部科学省が令和7年5月1日現在で実施した調査によると、全国の公立小中学校の体育館等(武道場を含む)における空調(冷房)設備の設置率は22.7%。
前回調査(令和6年9月)から3.8ポイント上昇したものの、依然として4校に1校も導入されていないというのが現実です。
中でも注目すべきは、避難所に指定されている体育館の設置率が23.7%にとどまっている点。
災害時に最も多くの人が集まる場所でありながら、空調が整っていない施設が大多数を占めています。
この数字は、単なる快適性の問題ではありません。
「安全の格差」といっても過言ではない状況です。
たとえば都市部では新設・改修時に空調を導入するケースが増えていますが、地方では財政的・構造的な制約から設置が難しい学校も多く、地域間で温度差が生まれています。
また、学校施設は築30年以上の老朽化建物が多く、天井の高さや断熱性能の不足など、物理的な制約も大きな壁となっています。
空調を設置するには電気容量の増設や配管ルートの確保、天井補強など、ただエアコンを取り付けるだけでは済まないケースがほとんどです。
一方で、全国的な「猛暑日」の増加は止まりません。
環境省のデータによれば、真夏日に分類される30℃以上の日数はこの10年で平均約1.3倍に増加。
地域によっては体育館の室温が40℃近くに達することもあり、「授業が成立しない」「熱中症の危険で部活を中止せざるを得ない」といった声も後を絶ちません。
つまり、いまの日本では「体育館に空調がない」こと自体がリスクになりつつあります。
この章では現状の数字を見てきましたが、次章では「ではなぜ、ここまで空調設置が進まないのか?」
その理由を構造・費用・運用の3つの視点から掘り下げていきます。
なぜ設置が進まないのか? 3つの課題

体育館への空調設置がなかなか進まない背景には、大きく分けて3つの課題があります。構造上の問題、費用面の問題、そして運用面での難しさです。それぞれを順に見ていきましょう。
構造面の課題 ― 冷やしても暖めても逃げてしまう空間
体育館は一般の教室とはまったく異なる構造をしています。天井が高く、広い空間を持つため、空気の循環が難しいのが最大の特徴です。冷暖房を入れても、冷気や暖気が上部に滞留してしまい、床付近の温度はなかなか安定しません。また、断熱材が十分でない建物が多く、外気温の影響を受けやすい点も課題です。特に築年数の古い体育館では、壁や屋根の断熱性能がほとんどないケースも多く、せっかくの空調も効率が悪くなってしまいます。
費用面の課題 ― 設備だけでなく、インフラ改修にもコストがかかる
体育館は空間が大きい分、必要な空調機の規模も大きくなります。1台あたり数馬力クラスの業務用エアコンを複数台設置することが一般的で、その設備費用はもちろん、ガス及び電源の確保や配管・ダクト工事、天井補強、
外壁の貫通工事なども必要です。導入費用は数百万円から数千万円規模にのぼり、自治体の予算を圧迫する要因となっています。さらに、運転にかかる電気代・ガス代、定期メンテナンスのコストも無視できません。教育現場では教室やトイレの改修、ICT環境整備など優先度の高い課題が多く、体育館の空調はどうしても後回しにされがちです。
運用面の課題 ― 多目的利用ゆえの“誰がどう使うか”問題
体育館は授業や部活動のほか、地域開放や避難所としても利用される多目的空間です。そのため、誰が空調を操作するのか、どのタイミングで運転するのかといったルール作りが必要になります。電気代の負担をめぐって学校と自治体、地域団体との調整が難航するケースも少なくありません。また、長時間運転によるフィルター清掃や点検など、維持管理体制の整備も欠かせません。特に天井高が10mを超える体育館では、メンテナンスのための高所作業が必要になるため、専門業者による定期点検が前提になります。
これら3つの課題は一見すると導入を難しく見えますが、実際には全国で着実に改善の動きが進んでいます。次章では、「それでも空調が必要とされる理由」を、教育と防災の両面から考えていきます。
それでも必要な理由 ― 子どもの安全と地域の安心

体育館に空調を導入することは、単なる快適性の追求ではありません。そこには、子どもたちの命を守り、地域の安心を支えるという明確な理由があります。
熱中症事故の防止 ― 「我慢」では済まされない現場の現実
ここ数年、体育館での熱中症事故は全国各地で報告されています。夏場の屋内活動中に児童が倒れ、救急搬送されるケースも少なくありません。特に梅雨明け直後の高温多湿な時期は、外よりも体育館内の気温の方が高くなることもあります。体育の授業や全校集会、部活動などでは数十人が同時に運動するため、熱がこもりやすく、体調不良を訴える生徒が続出することもあります。「水分をこまめに」「休憩を多く」といった対応には限界があります。空調の整備は、熱中症を“防ぐ”唯一の確実な手段といえるでしょう。
災害時の避難所としての機能維持
体育館は災害時、地域住民の避難所として利用されます。地震や台風などの非常時に、数百人が長期間過ごす空間です。真夏の高温や真冬の冷え込みのなかで空調がない場合、体調不良や感染症リスクが高まります。特に高齢者や乳幼児、持病のある方にとっては深刻な環境となりかねません。避難生活の長期化を見据えると、空調設備は防災インフラの一部と位置づけるべきです。実際、文部科学省も「空調設備整備臨時特例交付金」の活用を促し、避難所機能を持つ体育館への空調整備を後押ししています。
冬場の寒さ対策 ― 「冷房」だけでなく「暖房」も命を守る
体育館の課題は夏だけではありません。冬の朝礼や卒業式、入学式など、冷えきった体育館で長時間座っていた経験がある人は多いでしょう。体育館は床面積が広く、外気の影響を受けやすいため、冷え込みが特に厳しくなります。暖房を導入すれば、低体温症や体調不良の予防にもつながります。特に特別支援学校や高齢者施設と連携する避難所では、暖房機能の確保が不可欠です。
教育環境の平等化 ― 地域格差をなくすために
都市部の新設校では空調付き体育館が増えていますが、地方や財政難の自治体では整備が遅れがちです。同じ日本の子どもたちであっても、地域によって教育環境に差が生まれているのが現状です。「暑くて授業ができない」「部活を制限するしかない」といった状況を放置すれば、教育の機会均等にも関わります。体育館の空調化は、すべての子どもが安全に学び、体を動かせる環境を整えるための基礎条件ともいえます。
体育館の空調は“ぜいたく品”ではなく、“命と防災を守るための社会的インフラ”です。次章では、実際に導入を検討する際に知っておきたい設計・施工のポイントを解説します。
実際に導入するには? 設計と施工のポイント
体育館の空調導入は、「大規模空間にどんな設備を、どう取り付けるか」という設計段階からの検討が欠かせません。単にエアコンを設置するだけでなく、建物全体の構造や運用を見据えたトータル設計が求められます。
大空間に対応できる空調方式を選ぶ
体育館のような天井高8〜12mの大空間では、一般的な壁掛けや天吊りエアコンでは風が届きません。そのため、大型業務用エアコン(パッケージエアコン)やガスヒートポンプエアコン(GHP)が採用されるケースが多くあります。GHPはガスを動力とするため、電気容量の少ない施設でも導入しやすく、災害時の電力負荷軽減にも役立ちます。一方で電気式(EHP)は細かな温度制御や運転モード切り替えが容易で、省エネ性能にも優れています。建物の条件や電力インフラの状況を踏まえ、最適な方式を選定することが重要です。
断熱改修や気流設計で効率を高める
体育館は冷暖房の効率を上げるために、断熱補強や気流のコントロールも欠かせません。屋根面に断熱材を追加したり、壁面の隙間を塞いだりするだけでも、冷暖房効果は大きく改善します。また、シーリングファン(大型循環ファン)を併用し、天井付近に滞留する暖気や冷気を均等に循環させる方法も効果的です。空間を“全体で冷やす・暖める”のではなく、授業・集会などの使用エリアを絞って運転するゾーン制御を導入することで、ランニングコストの削減も実現できます。
電気容量・構造上の制約を事前に確認
体育館の空調導入で意外と見落とされがちなのが、電気容量の不足です。既存の分電盤や配電ルートが大出力エアコンに対応していないケースも多く、事前の電気設備調査が不可欠です。場合によっては受電設備の増設や幹線ケーブルの更新も必要になります。また、天井や梁の強度が不足している場合は、吊り金具や補強工事が必要になることもあります。設計段階で構造・電気・配管の3要素をしっかり検証し、長期的な運用に耐える安全設計を行うことが求められます。
メンテナンス性を考慮した配置計画
一度設置すれば終わりではありません。空調設備はフィルター清掃や点検、ガス量確認など定期メンテナンスが欠かせません。特に体育館は天井が高いため、高所作業車や足場を使わないと整備できない位置に設置してしまうと、維持費が大きくなります。長期的に見て安全かつ効率的にメンテナンスが行える配置計画を立てることが重要です。また、リモート制御やCO₂センサー連動など、最新の制御システムを導入することで、運転時間の最適化や省エネ化も期待できます。
補助金・交付金の活用を検討する
国や自治体では、体育館の空調整備に対して「空調設備整備臨時特例交付金」などの支援制度が設けられています。災害時の避難所機能を持つ施設であれば、申請の対象になるケースも多く、導入コストの一部を公的資金でまかなうことが可能です。設計段階から補助金の適用要件を確認し、費用負担を最小限に抑えることも、現実的な整備計画を立てるうえで重要なポイントです。
体育館の空調化には課題が多いものの、設計と施工の工夫次第で大きく実現性が高まります。次章では、全国で進む導入の動きと、ミヨシテックのような設備会社がどのように支援できるかを紹介します。
導入事例 ― 全国で進む空調整備の動き
体育館への空調導入は、全国的に徐々に進みつつあります。背景には、文部科学省による交付金制度の整備と、各自治体の防災意識の高まりがあります。特に令和6年から始まった「空調設備整備臨時特例交付金」の創設により、避難所機能を持つ体育館での整備が一気に加速しました。
自治体で進む「避難所機能強化」としての空調整備
たとえば大阪府や兵庫県では、「災害時における避難所環境の改善」を目的に、体育館空調の設置を計画的に進めています。特に近年の猛暑や大雨災害を受け、避難所としての体育館に求められる環境レベルは年々上がっています。空調設備の整備は“贅沢な快適性”ではなく、“災害時の生命線”として位置づけられています。
また、東京都内では、新築や改修工事のタイミングで空調導入を標準仕様化する動きも見られます。設計段階から断熱性能や気流設計を考慮することで、運転コストを抑えながら安定した室温を維持できる環境づくりが進んでいます。
学校教育現場での効果 ― 「授業の質」と「活動の安全性」向上
空調導入後の学校では、「集中力が続く」「授業が滞りなく行える」「熱中症リスクが激減した」といった声が上がっています。体育の授業だけでなく、入学式・卒業式などの学校行事も快適に実施できるようになり、児童・生徒だけでなく教職員からの評価も高い傾向です。特に部活動が盛んな学校では、夏場でも安全に活動できる環境が整い、生徒の健康被害や指導者の負担軽減にもつながっています。
省エネ型設備や再エネとの組み合わせも進行中
環境配慮の観点から、太陽光発電や蓄電池と組み合わせた運用を行う学校も増えています。昼間の授業時間帯に太陽光で発電した電力を空調に活用し、電力消費を抑える取り組みです。また、最新のGHP(ガスヒートポンプ)ではCO₂排出量を抑えた高効率モデルも登場しており、環境負荷の低減と快適性の両立が可能になっています。こうした技術革新が、体育館の空調整備をより現実的なものにしています。
公共施設全体への波及 ― “防災拠点”としての再評価
体育館の空調整備は、今や学校だけの話ではありません。自治体庁舎や地域センターなど、公共施設全体の防災拠点機能の強化として同様の取り組みが広がっています。地域の「安全拠点」としての体育館整備は、災害対応力の向上に直結します。これは単なる施設改修ではなく、地域インフラの再構築とも言える動きです。
全国の導入事例から見えてくるのは、空調整備が「快適さの向上」だけでなく「命と地域を守る投資」になっているということです。次章では、そうしたニーズに応えるために、ミヨシテックがどのような技術と体制で支援しているのかを紹介します。
ミヨシテックができること ― 学校・公共施設の空調工事実績
体育館や公共施設の空調整備には、電気・ガス・建築・制御といった複数分野の知識と技術が求められます。ミヨシテックは、大阪を拠点に住宅・法人の設備工事を手掛けてきた実績を生かし、学校・庁舎・医療施設などの大規模空間への空調導入工事にも対応しています。
GHP・EHPの両方式に対応した設計・施工力
ミヨシテックは、ダイキンプロショップとしてGHP(ガスヒートポンプ)・EHP(電気式ヒートポンプ)のどちらにも精通しています。建物の用途や電力容量、運用目的に応じて最適な空調方式を提案。特に体育館のような大空間では、GHPの高出力性能や部分運転制御を活かした設計を行うことで、効率的かつ安定した温度管理を実現します。また、既存建物への後付けにも柔軟に対応し、限られたスペースでの配管・配線ルート設計や重量計算にも専門技術を活かしています。
電気・ガス・ダクト・制御まで“一括対応”
体育館の空調化には、空調機器設置だけでなく、電気工事・ガス配管・制御システム設定など多岐にわたる工程が必要です。ミヨシテックはこれらをすべて自社一括で施工管理できるため、工期短縮・コスト削減・品質の均一化を同時に実現できます。特に改修工事では、授業や部活動を妨げないスケジュール調整も重要です。学校側と綿密に打ち合わせを行い、休校期間や休日施工など柔軟な工程対応を行っています。
省エネ・環境配慮型の設計提案
省エネ性能の高い機種選定や、シーリングファンとの連動、CO₂センサーによる自動制御など、環境負荷を抑えた空調計画も得意としています。自治体が求める脱炭素・防災型施設への対応として、太陽光発電や蓄電池との組み合わせ提案も可能です。また、運転効率を高める断熱改修・ゾーン制御・タイマー運転など、長期運用コストを見据えた設計を行っています。
公共施設特有の安全基準・申請にも対応
学校や庁舎などの公共施設では、民間建築とは異なる安全基準や行政手続きが求められます。ミヨシテックでは官公庁工事の経験を多数持ち、入札・設計協議・検査立会いまでの一連の流れを熟知しています。消防設備や換気基準に関する技術的助言も行い、法令に準拠した安全な施工を徹底します。
導入後の保守・メンテナンス体制も万全
空調設備は導入後のメンテナンスこそが性能維持のカギです。ミヨシテックでは、定期点検・清掃・ガス漏えい検査などを含むアフターメンテナンス契約を用意し、長期的に安心して運用できるサポート体制を整えています。異常時の緊急対応や部品交換なども自社技術者が迅速に対応し、トラブルによる運用停止を最小限に抑えます。
災害対応・防災型設備の提案力
「避難所としての体育館空調整備」という観点から、非常用発電機やガス供給ラインとの連携設計も行っています。災害時でも稼働可能なGHP+非常用電源の組み合わせは、BCP(事業継続計画)対策としても高い評価を受けています。万一の停電時にも、最低限の冷暖房を維持できる仕組みづくりが可能です。
ミヨシテックは、単なる空調工事業者ではなく、“地域の安心を支える技術パートナー”として、教育現場や公共施設の課題解決に取り組んでいます。次章では、体育館空調整備がもたらす未来の価値を総括します。
体育館の空調は“未来へのインフラ”

体育館に空調を導入することは、もはや“ぜいたく”ではありません。
それは、子どもたちの命を守り、地域の安心を支えるための社会的インフラ整備です。
猛暑や寒波の中で「我慢する」時代は終わりつつあります。
熱中症や寒冷による体調不良を防ぐことはもちろん、災害時に避難所として安全に人を受け入れるためにも、体育館の空調化は不可欠な要素となっています。
また、空調を整備することで、授業や行事の質が向上し、教育の平等性を確保することにもつながります。
「暑くて授業にならない」「寒くて集中できない」――そんな状況をなくし、すべての子どもたちが安心して過ごせる環境を整えることは、未来への投資そのものです。
今後、国の交付金制度や省エネ機器の普及によって、体育館空調の導入はますます現実的になっていくでしょう。
ミヨシテックでは、学校・自治体・設計事務所などと連携しながら、現場の課題に合わせた最適な空調計画を提案しています。
- GHP・EHPの両方式に対応
- 断熱・電気・ガス工事まで一括施工
- 補助金活用のサポート
- 災害時も安心の防災型空調提案
体育館の空調化は、「今すぐ快適になる」だけでなく、「10年、20年先の地域の安心」を支える取り組みです。
もし、空調導入をご検討の学校関係者・自治体の方がいらっしゃいましたら、ぜひ一度ミヨシテックへご相談ください。
私たちは、空調を通じて“未来のあたりまえ”をつくります。